日本の水族館や動物園で人気のペンギンですが、一言でペンギンの言っても、その種類は多岐にわたります。
今回の記事では、ペンギンの種類別に、寿命と生態について、性格の違いについても紹介していきます。
ペンギンの種類別寿命
日本で見かけることが多い4種類のペンギンの寿命をまとめました。
ケープペンギン
野生のケープペンギンの平均寿命は、約10年と言われていますが、水族館などで飼育されているケープペンギンは、寿命が長く、約15〜20年となります。
水族館は、飼育環境が整っていることと外敵に襲われる心配がないことで、長生きする傾向にあるようですね。
皇帝(エンペラー)ペンギン
体が大きい皇帝(エンペラー)ペンギンの平均寿命は、野生の個体でも15年から20年と長めです。
日本国内の水族館だと、長崎水族館で1964年から1992年にかけて28年と5ヶ月間生きた「フジ」という個体が確認されています。
皇帝(エンペラー)ペンギンは、環境が整えば、40歳または50歳近くまで生きることも可能だと言われています。
マゼランペンギン
胸の部分の黒いラインが2本になっていることが特徴的な中型のペンギンであるマゼランペンギン。
野生のマゼランペンギンの平均寿命は、約12~25年年と幅があります。
一方、水族館などで飼育されているマゼランペンギンは、非常に寿命が長くなり、最大で30年くらい生きられることもあるようです。
フンボルトペンギン
寒いところに住んでいるイメージが強いペンギンですが、フンボルトペンギンの生息地は南米であり、寒いところは苦手です。
フンボルトペンギンは、野生下の個体でも20年、飼育下になると25~30年とかなり長生きです。
長寿情報としては、桐生が岡動物園で40年、葛西臨海水族園で31年2ヶ月生きた個体が確認されています。
フンボルトペンギンは、日本の気候でも飼育しやすいため、日本の動物園や水族館でもっとも見かけることが多いペンギンですね。
ペンギンの生態
現在、ペンギンは6属18種、存在します。
ペンギンは、昔に絶滅してしまった種類もたくさんあり、かなり減ってしまったようです。
一言でペンギンと言っても、小型のものから大型のものまでさまざまな種類があり、体高は40~130cm、体重は1~45kgと幅広いです。
ちなみに、もっとも小型なのが、コガタペンギンで、もっとも大型なのが皇帝(エンペラー)ペンギンとなります。
では、そんなペンギンの生態について紹介します。
ペンギンといえばひれでバランスを取りながらヨチヨチと歩くかわいらしい姿が目に浮かびますが、ペンギンには、腹ばいになった状態で雪面や砂浜を滑るトボガンと呼ばれる移動方法あります。
また、ペンギンは陸上では動きが遅いですが、水中での動きは敏速。
猛スピードで泳ぎながら、アジやイワシなどの魚を捕ります。
水中を泳ぐ姿は、まるで空を飛ぶ鳥のようで、その姿を見ると、ペンギンが生物学的に鳥であることもすんなりと納得できるはずです。
そして、野生のペンギンは、常に他の肉食動物に狙われる危険にさらされているため、集団行動をしています。
陸から海へ入るとき、海から陸にあがる時、ペンギンたちは、まず1羽が先行して安全確認をし、危険がないことを確認します。
群れ全体の被害を最小限に抑えるための行動が徹底されているのですね。
ペンギンの性格の違い
では、ペンギンの種類ごとに性格の違いを見ていきましょう。
まず、アフリカ大陸の南部の沿岸に生息しているケープペンギンの性格は、ちょっぴり攻撃的。
敵とみなした相手には、くちばしやフリッパーで立ち向かいます。
自分より大きい人間に対しても恐れることはありません。
マゼランペンギンとフンボルトペンギンの性格も、警戒心が強く、敵には容赦なく噛み付きます。
しかし、野生で生息しているマゼランペンギンやフンボルトペンギンと人間が近づく機会はあまりないため、野生での調査はあまり進んでいないのが現状のようです。
一方、マイナス60度という厳しい環境の南極大陸に生息している皇帝(エンペラー)ペンギンの性格は社交的で、攻撃性は低いとされています。
マイナス60度という厳しい環境の中、仲間と協力しあい、集団で生活している皇帝(エンペラー)ペンギンですから、なわばり意識がなく、優しい性格をしているのでしょう。
おわりに
今回は、日本でよく見られるペンギンの種類について、寿命や性格をまとめました。
日本人が大好きなペンギンですが、大きさや性格、野生の生息地などは、種類によってさまざまで、一言でペンギンと言っても、奥が深いですね。
ペンギン好きの方は、ぜひいろんな水族館や動物園に足を運んで、さまざまな種類のペンギンについて観察してみてくださいね。

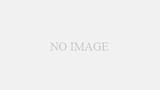

コメント